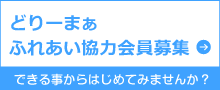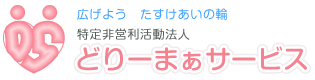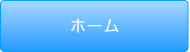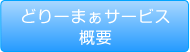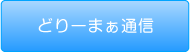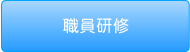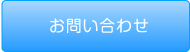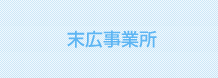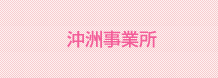早いものでもう年の暮れとなりましたが、地域の皆様及び関係者各位におかれましては、日ごろからのご指導ご協力に心から感謝致します。
高市新首相の所信表明演説文を読んでみました。印象に残った内容を挙げてみます。
冒頭、「強い経済を作る。」そして、「日本列島を強く豊かにしていく。」とありました。また「政治の安定なくして、力強い経済政策も、力強い外交・安全保障政策も推進していくことはできない。」と訴えられています。また、人口減少・少子高齢化を乗り切るためには、社会保障制度について、「攻めの予防医療」を徹底し、健康寿命の延伸をはかり健康課題への対策を加速するといわれています。
さて、2025年版の自殺対策白書では、24年の15〜29歳の若者の自殺者は3125人で、5年連続で3000人を超えています。小中学生の不登校も文部科学省によりますと、同年度に30日以上欠席した児童生徒は35万人を超え、いじめの認知件数も約77万件と過去最悪となったようです。高齢者分野においては今、頼れる家族がいない一人暮らしの高齢者が増えて問題となっています。人口が縮小しても、必要な働き手はむしろ増える見通しで、リクルートワークス研究所は、40年の労働力不足は1100万人に達するようです。
このようなことからも昨今、「ケアの倫理」が各方面で注目されています。ケアが行き届いているときには、誰かが何に対してどのようなケアをしているかに気づくことはほとんどありませんが、ケアが欠損した今まさに、日本社会はさまざまな局面で気づかざるを得ません。
今年のノーベル化学賞の北川進さんが語った「無用の用」ですが、これは材木などに使えない木がそれゆえ切られることもなく巨木になりえたといった数々の寓話で説かれています。世間的な価値観だけでものごとははかれないという趣旨です。有名な地面の話で、必要だけを考えれば足をつける面積しか要らないわけだが、そうではなく、地面は広いから役立つのだという教えです。すなわち広く大きく構えたらどうかという考え方を表現しているのかもしれん。感情や雰囲気に流されがちな今、冷静を保つ助けになりそうです。
法人としては、今後どういった局面においても力強さとその先にある豊かさを目指し、大きく構えた運営を目指していかねばならないと改めて気づかされました。
令和7年12月1日
理事長 山口浩志
|